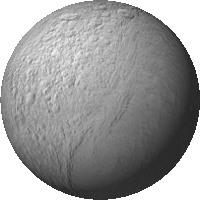このブログを御覧になっている皆様、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
年の初めは、知人に出している年賀状の紹介から始めます。
![2016年 日食年賀状]() 2016年 日食年賀状陽光彩雲
2016年 日食年賀状陽光彩雲 【ようこう さいうん】
〔吉兆の日の光〕
ようこう【陽光】とは、太陽の光。日光
さいうん【彩雲】とは、光環と同じく、太陽や月の光が微小な水滴や氷晶による回折現象で、淡い赤や緑で縁どられるか、部分的に輝いて見える雲。主に巻雲、巻積雲や高積雲などで見られる。昔は吉兆として、慶雲、景雲、紫雲(しうん)、瑞雲(ずいうん)などの名前で呼ばれた。
昨年も今年も金欠で皆既日食遠征には行かれそうもないので、ネットから公共に展示していた写真を拝借しました。
ほんの一瞬見られるコロナを陽光に例えました。![2016年 冥王星年賀状]() 2016年 冥王星年賀状
2016年 冥王星年賀状今年だけ提供できる冥王星探査機ニュー・ホライズンズが撮影した写真に遊び心を加えた絵を拝借して年賀状にしました。隣の星は衛星カロンです。
![2016年 ねぷた年賀状]() 2016年 ねぷた年賀状熈光豊楽
2016年 ねぷた年賀状熈光豊楽 【きこうほうらく】
〔光のひろまりはゆたかにうきうきさせる〕
青山・宮園連合ねぷた 絵師・三浦呑龍
水滸伝 中箭虎 丁得孫毒蛇を討つ
個人的には、昨年一番のねぷた絵の出来ではないかと思いました。大蛇が生き生きと動くように見えているさまは、三浦呑龍先生の絵ならではだと思います。
丁 得孫(てい とくそん)は、中国の小説で四大奇書の一つである『水滸伝』に出てくる登場人物。梁山泊第七十九位の好漢で、地速星の生まれ変わり。渾名は
中箭虎(ちゅうせんこ)で、顔から首にかけてあばただらけであり、さながら矢傷を受けた虎という意味を込めて名付けられた。飛叉(刺又の投げ槍)の使い手。東昌府で龔旺と共に張清の副将として仕えていた。
東昌府に盧俊義率いる梁山泊軍が攻めてきた際、龔旺とともに張清の副将として出陣し、張清の活躍により盧俊義軍を大いに苦しめた。さらに東平府を落とした宋江率いる梁山泊軍も加わりこれを迎え撃つが、董平に張清が互角に戦っていると、索超が董平の援護に近づいてきたので龔旺とともに止めに向かった。しかし、今度は敵陣から呂方と郭盛が出て来て丁得孫に立ち塞がり、必死に応戦するも燕青に馬を矢で射られて転倒し、そのまま生け捕られる。龔旺も生け捕られ、さらに張清も生け捕られて投降し梁山泊入りしてしまったため、丁得孫も龔旺とともにそれに従って梁山泊入りする。
入山後は、龔旺とともに歩軍将校に任命される。その後も龔旺とともに戦場に赴き、朝廷招安後の遼国戦や田虎討伐と王慶討伐にも参戦する。方臘討伐の歙州攻めで敵の夜襲を予想した朱武により草むらで伏兵として身を潜めて待ち伏せして敵を撃退するも、その際に
丁得孫は毒蛇に脚を噛まれてしまい、そのまま死亡するというあっけない最期を遂げる。![2016年 桜年賀状]() 2016年 サクラ年賀状・・・この写真は2014年4月に撮ったものですが、堀に映った岩木山が綺麗でした
2016年 サクラ年賀状・・・この写真は2014年4月に撮ったものですが、堀に映った岩木山が綺麗でした![2016年 鉄道年賀状]() 2016年 鉄道年賀状
2016年 鉄道年賀状1997年春に南部縦貫鉄道が休止ののち廃止となりました。
昭和末期に野辺地駅で撮影した写真の出来が良くて今年の年賀状にしました。

 最も環の密度が高い部分は、A環及びB環であり、これらはカッシーニの間隙によって隔てられている(1675年にジョヴァンニ・カッシーニによって発見された)。これに沿って1850年に発見されたC環があり、これらでメインリングを形成する。メインリングは希薄な塵のリングと比べて、密度が高く、粒子の大きさも大きい。後者にはD環が含まれ、土星の雲の上端まで達している。G環、E環及びその他の環は、メインリングよりも外側にある。これらの希薄な環は、しばしば1μm程度の小さな粒子で構成されるが、その化学組成は、メインリングと同様にほぼ純粋な水でできた氷である。狭いF環は、A環のすぐ外側にあり、カテゴライズが難しい。非常に密度の高い部分があるが、非常に多くの塵サイズの粒子を含んでいる。
最も環の密度が高い部分は、A環及びB環であり、これらはカッシーニの間隙によって隔てられている(1675年にジョヴァンニ・カッシーニによって発見された)。これに沿って1850年に発見されたC環があり、これらでメインリングを形成する。メインリングは希薄な塵のリングと比べて、密度が高く、粒子の大きさも大きい。後者にはD環が含まれ、土星の雲の上端まで達している。G環、E環及びその他の環は、メインリングよりも外側にある。これらの希薄な環は、しばしば1μm程度の小さな粒子で構成されるが、その化学組成は、メインリングと同様にほぼ純粋な水でできた氷である。狭いF環は、A環のすぐ外側にあり、カテゴライズが難しい。非常に密度の高い部分があるが、非常に多くの塵サイズの粒子を含んでいる。