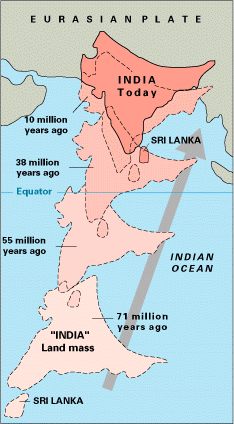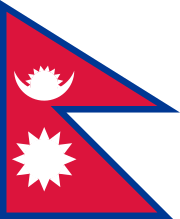February 14, 2014, 1:00 pm
Procedural landscape using Perlin Noise パーリンノイズとは、コンピュータグラフィックスのリアリティを増すために使われるテクスチャ作成技法。擬似乱数的な見た目であるが、同時に細部のスケール感が一定である。このため制御が容易であり、各種スケールのパーリンノイズを数式に入力することで多彩なテクスチャを表現できる。パーリンノイズによるテクスチャは、CGIで自然な外観を物に与えるためによく使われる。
パーリンノイズは (x,y,z) または (x,y,z,time) の関数として実装され、事前に計算された勾配に従って内挿を行い、時間的/空間的に擬似乱数的に変化する値を生成する。Ken Perlin は2002年に実装を改善し、より自然に見えるようにした。
パーリンノイズは、コンピュータグラフィックスで炎や煙や雲を表現するのによく使われている。また、メモリ使用量が少ないため、メモリ容量が小さい場面でのテクスチャ生成にも使われ、パソコンゲームでのリアルタイムCG生成時にGPU上で使われることが増えている。
Gimpで作成出来るSolid noise
↧
February 15, 2014, 1:00 am
↧
↧
February 15, 2014, 1:00 pm
↧
February 16, 2014, 1:00 am
↧
February 16, 2014, 1:00 pm
↧
↧
February 17, 2014, 1:00 am
↧
February 17, 2014, 1:00 pm
Earth 100 Million Years From Now インド亜大陸はインド半島とも言い、南アジアのインド・バングラデシュ・パキスタン・ネパール・ブータンなどの国々を含む亜大陸・半島。かつては独立したインド大陸であった。アルフレート・ヴェーゲナーの大陸移動説やプレートテクトニクスによると、パンゲア大陸から分離・移動してユーラシア大陸に衝突し、ヒマラヤ山脈が隆起したとされる。現在もインド亜大陸は北上し続けている。
ヒマラヤ山脈は地球上で最も若い山脈の一つである。現代のプレートテクトニクス理論によると、ヒマラヤ山脈はインド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートの間の沈み込みで起きた大陸同士の衝突による造山運動から生じた。衝突は7,000万年前後期白亜紀に始った。そのころインド・オーストラリアプレートは15cm/ 年の速度で北上し、ユーラシアプレートと衝突した。
約5,000万年前、このインド・オーストラリアプレートの速い動きによって海底の堆積層が隆起し、周縁部には火山が発生してインド亜大陸とユーラシア大陸の間にあったテチス海を完全に閉ざした。 これらの堆積岩は軽かったので、プレートの下には沈まずにヒマラヤ山脈を形成した。 今もインド・オーストラリアプレートはチベット高地の下で水平に動いており、その動きは高地に更に押し上げている。 ミャンマーのアラカン山脈とベンガル湾のアンダマン・ニコバル諸島もこの衝突の結果として形成された。かつて海だった証拠として、高山地帯で貝などの化石が発見される。
今もインド・オーストラリアプレートは67 mm/年の速度で北上しており、今後1,000万年の間でアジア大陸に向って1,500 km移動するだろうと考えられている。この動きのうち約20 mm/年の分は、ヒマラヤの南の正面を圧縮することによって吸収される。結果として約5mm/年の造山運動が発生し、ヒマラヤ山脈を地質学的に活発にしている。 このインド亜大陸の動きにより、この地域は地震の多発地帯となっている。
120億年前のインド亜大陸
↧
February 18, 2014, 1:00 am
↧
February 18, 2014, 1:00 pm
↧
↧
February 19, 2014, 1:00 am
マスクに裏表があるって本当?他、役立つ花粉雑学集!<Yahoo広告企画特集>
↧
February 19, 2014, 1:00 am
Pangong Tso (Lake), Ladakh ヒマラヤ山脈には何百もの湖が点在している。大部分の湖は5,000 m未満の高度に存在し、高度が上がるとともに湖の規模は小さくなっていく。 最大の湖はインドとチベットの境界に横たわるパンゴン湖で、高度4,600 mに位置し、幅8 km、長さは134 kmに及ぶ。
パンゴン湖は中華人民共和国チベット自治区ルトク県とインドジャンムー・カシミール州ラダック県との中印国境に位置するアジア最大級の汽水湖である。
全長は150キロ余り、面積は604㎢、南北の平均幅は2-5kmだけ、最も狭い所は5mだけ。水深は最深部で約300m。標高4250mの位置にあり、塩湖(インド側)としては世界でもっとも高い場所にある。塩湖にもかかわらず、冬は1mに及ぶ厚い氷が張る。
東側の三分の二は中国に属して、西側の三分の一(約50km)はインドに属する。中国の境界内にあるパンゴン湖は淡水湖で、清らかで甘美で、水色は青緑であると中国側では発表されている。一方、インド境界内にあるのは塩湖で、水は臭くて飲まない。周囲を4000~6000m級のヒマラヤの山々で囲まれた内湖で、以前はインダス川の支流と繋がっていたが、現在は自然の積載によって閉じている。小さな甲殻類がいるのみで、魚は棲息していない。
パンゴン湖の眺め
↧
February 19, 2014, 1:00 pm
↧
February 20, 2014, 1:00 am
↧
↧
February 20, 2014, 1:00 pm
↧
February 21, 2014, 1:00 am
応募総数33,605句の頂点に輝くのは一体どの句!?
↧
February 21, 2014, 1:00 am
Flight to Mount Everest 1865年、英国インド測量局長官だったアンドリュー・ウォー(Andrew Waugh)によって、前長官ジョージ・エベレストにちなんだ英語名がつけられた。ウォーは地元民の呼び名がわからないとした上で、手記に以下のように記している。当時、ネパールもチベットも外国人の立ち入りを認めていなかった。
尊敬する前長官のサー・ジョージ・エベレスト大佐 (Colonel Sir George Everest) は、すべての地形に現地での呼称を採用するよう、私に教えてきた。しかしこの山には、おそらく世界最高峰であろうこの山には、現地での呼称を見いだすことができなかった。もし仮にそれがあったとしても、私たちがネパールへの立ち入りを許可される前に、それが見つかることはないだろう。今のところ、この高峰を名付ける特権と責任とは、同等に私に委譲されているものと思う。この山の存在が、市民と地理学者に広く知られ、文明国家に深く浸透するかは、この高峰の名称いかんにかかっている。
1960年代、ネパール政府はエベレストには元々現地での呼び名が存在していたことを発見した。これまでこの存在が知られていなかったのは、エベレストがカトマンズ盆地とその周辺地域の民族に知られておらず名づけられていなかったからで、政府はエベレストの名称を探し出すことに着手した。しかし、シェルパ族の間での名称・チョモランマはネパール統一国家の考えに反するとして採用されなかった。現在のネパール名・サガルマータはネパールの著名な歴史学者、バブラム・アチャリャ (Baburam Acharya) によって考案されたものである。しかしその後もしばらくの間は、カトマンズから東方に高く見えるガウリ・シャンカルがサガルマータだと思っている人が多かった。
2002年、中国の人民日報は西洋でも英語名エベレストの使用をやめて、チベット名のチョモランマを採用すべきと主張する記事を掲載した。人民日報はチョモランマというチベット名は280年以上前の地図にも記載されており、英語名よりも歴史が長いと主張している。
エベレストを中心に捉えたパノラマ写真
↧
February 21, 2014, 1:00 pm
Our trip to Nepal ネパール連邦民主共和国、通称ネパールは、南アジアの共和制国家。2008年に王制廃止。
東、西、南の三方をインドに、北方を中国チベット自治区に接する西北から東南方向に細長い内陸国である。国土は世界最高地点エベレスト(サガルマータ)を含むヒマラヤ山脈および中央部丘陵地帯と、南部のタライ平原から成る。ヒマラヤ登山の玄関口としての役割を果たしている。
多民族・多言語国家(インド・アーリア系の民族と、チベット・ミャンマー系民族)であり、民族とカーストが複雑に関係し合っている。また、宗教もヒンドゥー教(元国教)、仏教、アニミズム等とその習合が混在する。経済的には後発開発途上国である。農業を主たる産業とする。ヒマラヤ観光などの観光業も盛んである。
中国国境地帯にはサガルマタ(英国呼称エベレスト)を始めとする8000m級の高峰を含むヒマラヤ山脈が存在する。そのため高山気候となっている。一方、インドとの国境地帯は「タライ」「テライ」または「マデス」といわれる高温多湿の平原地帯で肥沃である。その中間には丘陵地帯が広がる。最高所はエベレストで標高8850m。最低所は標高70mである。面積は140,800km²。本州を除いた日本(北海道+九州+四国)に等しい。
ネパールの位置
↧
↧
February 22, 2014, 1:00 am
その方法、理論として学んでみませんか?<2014年4月入学生募集中!>
↧
February 22, 2014, 1:00 am
↧
February 22, 2014, 1:00 pm
↧
 パーリンノイズとは、コンピュータグラフィックスのリアリティを増すために使われるテクスチャ作成技法。擬似乱数的な見た目であるが、同時に細部のスケール感が一定である。このため制御が容易であり、各種スケールのパーリンノイズを数式に入力することで多彩なテクスチャを表現できる。パーリンノイズによるテクスチャは、CGIで自然な外観を物に与えるためによく使われる。
パーリンノイズとは、コンピュータグラフィックスのリアリティを増すために使われるテクスチャ作成技法。擬似乱数的な見た目であるが、同時に細部のスケール感が一定である。このため制御が容易であり、各種スケールのパーリンノイズを数式に入力することで多彩なテクスチャを表現できる。パーリンノイズによるテクスチャは、CGIで自然な外観を物に与えるためによく使われる。