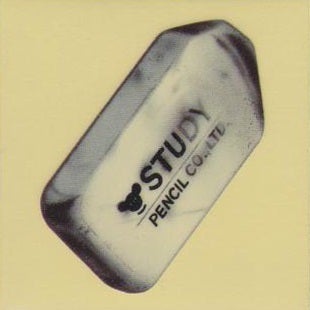November 10, 2014, 1:00 am
![帽子掛け]() 帽子掛け
帽子掛け![帽子掛け]()
どっきりシールが作られた1977(昭和52)年は、このような帽子掛けも多かったと思いますが、今では上の画像の例にもあるように大変モダンな帽子掛けがあります。普段の生活で帽子を必要としないので、帽子掛けについての思い入れは特にありません。
しかし冬に寒くなると、流石に厚手の帽子は必要です。銀河鉄道999に登場する
メーテルが被っている
パパーハと言う帽子なら被りたいのですが、少し丸くなった布製の黒い帽子しかないので真冬はそれを被って街に出ています。そんな季節が段々近づいてきました。どっきりシールの帽子掛け
・・・もう少しデザインの良さを追求して欲しいです。
![No.43 ぼうしかけ]()
![No.43 ぼうしかけ 裏]() No.43 ぼうしかけ
No.43 ぼうしかけ
↧
November 10, 2014, 1:00 pm
↧
↧
November 11, 2014, 1:00 am
THE MAKING (123)ノートができるまで ![モレスキンの手帳]()
ノートブック(notebook)は、複数の紙を金具や糊で束ねた文房具である。帳面、筆記帳などと呼ばれる。なお、ノートというだけでノートブックを指す用法は和製英語である。英語のノート(note)の意味は、短い記述、書きつけ、覚え書き、注釈などで、ノートブックの意味はない。
多種多様なノートがあるが、文章あるいは説明に供する図形を書くのが主目的であり、絵を書くためのスケッチブックなどとは区別される。ノートの表紙、裏表紙を除いた紙の色は一般的には白色で、表面は無地のもの、あるいはあらかじめ横罫や縦罫、マス目が印刷されているものなどがある。
![No.45 ノートのこげ]()
![No.45 ノートのこげ 裏]() No.45 ノートのこげ 裏
No.45 ノートのこげ 裏
↧
November 11, 2014, 1:00 pm
石油系ドライクリーニング ![ドライクリーニング]()
ドライクリーニングとは、洗剤を溶かした水の代わりに工業ガソリンなどの有機溶剤を使って洗濯すること。水を使って行う洗濯に比べ、油脂の汚れをよく落とし衣類の伸縮が生じにくい。
汗などの水溶性の汚れは落ちにくく物によっては色落ちしたり、素材自体を傷めたりすることがあるため、使用する際にはドライクリーニングが可能な素材なのかどうかをよく注意する必要がある。ドライクリーニングを専門に行っている業者はクリーニング業法の「クリーニング業」とされ、都道府県知事への届出や確認など法的な規制を受ける。
![No.46 クリーニングのふだ]()
![No.46 クリーニングのふだ 裏]() No.46 クリーニングのふだ
No.46 クリーニングのふだ
↧
November 12, 2014, 1:00 am
チャコル&マーブル育児日記 ~生後49日目 せんたくばさみ![洗濯バサミ]()
洗濯ばさみとは洗濯物や布団などを干す場合に落下しないよう挟んでとめる留め具。洗濯物を乾燥させるためにヒモや物干しざおにかけるとき、掛けた洗濯物を落ちないように固定するために使われ、様々なデザインや色彩がある。洗濯ばさみはそのスプリングの効果によって、子供達の興味をそそり、様々な自由工作の材料として用いられる。
今日では工場で安価に大量生産されたプラスチック製のものがほとんどで、2つのプラスチック部位をインターロックで組み合わせたものが一般的。レバーを押さえることによって留め具の部分が開き、手を離すと固定される仕組みとなっている。
![No.47 せんたくばさみ]()
![No.47 せんたくばさみ 裏]() No.47 せんたくばさみ 裏
No.47 せんたくばさみ 裏
↧
↧
November 12, 2014, 1:00 pm
安全ピン貫通マジック![安全ピン]()
安全ピンは、複数枚の布をとめるために使われる金属製器具。布同士を留めたり、服にバッジを留めたりする際に用いられる。
まっすぐな形をした留め針とは異なり、安全ピンは鋭い針の先を金具の中に引っ掛けておくことで、体や指に不用意に刺さらないようにできている。安全ピンは鋭いピンのある部分と、ピンの先を収納する留め金の付いた部分からなっており、根本にあるバネによって、留め金にかかっていないピンは開いた状態に戻るようになっている。
![No.48 あんぜんピン]()
![No.48 あんぜんピン 裏]() No.48 あんぜんピン 裏
No.48 あんぜんピン 裏
↧
November 13, 2014, 1:00 am
Sexy Ariana ![ビールの王冠]()
マリア・・・本名マリア・パナヨトヴァ・アンドノヴァ(ブルガリア語:Мария Панайотова Андонова)は、ブルガリア中南部スタラ・ザゴラ出身のポップ・フォーク歌手。
2004年、ブルガリアのビール「Ariana」のCMに起用された。内容はマリアが胸でビールの栓を開け、そして彼女がネックレスとしてつけている栓抜きが顕わになるというものである。このCMにちなんで彼女はマーラ・オトヴァラチカタ(Mara Otvarachkata - 栓抜きマリア) のニックネームがつけられた。
![No.49 ビールのせん]()
![No.49 ビールのせん 裏]() No.49 ビールのせん
No.49 ビールのせん
↧
November 13, 2014, 1:00 pm
家庭塗料・アサヒペン CM ![塗料]()
塗料とは対象物を保護・美装、独自な機能を付与するため、その表面に塗り付ける材料のこと。日本には古くから漆塗の歴史はあったが、洋式塗料の歴史は明治初頭に始まる。日本では家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規程に定めがある。
塗料には用途に応じて様々なタイプがある。例えばペンキやニスに代表されるように、一般に液状で溶剤の揮発・乾燥によって固化・密着し、表面に塗膜を形成して対象物の美観を整え保護するもの。オイルステインに代表される粘度が低く、木の内部に浸透し材料の劣化を防ぎ着色するもの等々。建築物や構造物、自動車、鉄道などの車両、船舶、電気機械、金属製品、ガーデニング用品、家具、皮革、模型など多様な用途ごとに特化したものがある。
![No.50 ペンキ]()
![No.50 ペンキ 裏]() No.50 ペンキ 裏
No.50 ペンキ 裏
↧
November 14, 2014, 1:00 am
↧
↧
November 14, 2014, 1:00 pm
↧
November 15, 2014, 1:00 am
![]() |
| ANA JCBカード。今なら、最大合計33000マイルもらえるキャンペーン実施中 |
![]()
↧
November 15, 2014, 1:00 am
Sesame Street - Kermit talks about hands![指]()
指はそれを所有する人間、動物によっては構成要素や構造が様々であり、その機能に見合った生活をしている。基本的には四肢を持つ脊椎動物に存在するもので、それ以外の動物の場合、類似の構造をこう呼ぶ場合があるが、普遍性のあるものはない。
人を含め左右の手あるいは腕や足にそれぞれ生物固有の本数と形状で備わり、付属器官として爪、指紋、外分泌器などがあり、外部への攻撃やモノの把持、触覚、歩行における体重移動の補助機関などとして働く。
形態学的に指は多くの関節と腱と筋肉から構成され、複雑な動きに耐えるモノが多い。また、その先端には角質化した爪があり、これも様々な形があって、指の働きを補助する。
指は手の付属器官として、健康については手を基調に語られることが多い。知覚神経や運動神経が鋭敏である指の固有の働きは人の日常生活に欠かすことのできないものが多く、その重要性は高い。
付属器官である爪は代謝が早く爪の裏には毛細血管が走っており、その色が日常的に観察しやすい。その時々の体調を現しやすく、様々な健康診断の指標となり健康のバロメーターとも呼ばれる。
また指には固まりやすい関節部が多いため、指は使わないと1週間ほどで動きがかなり鈍くなってしまう。老化に伴い関節部の代謝は悪くなるため老後もその機能を保持するためには、細目に動かすことが求められる。
![No.51 ゆび]()
![No.51 ゆび 裏]() No.51 ゆび
No.51 ゆび
↧
November 15, 2014, 1:00 pm
![妻・セツ子]() 妻・セツ子
妻・セツ子![面白いスーパーの値札]()
値札(英: price tag)は、小売店側が客に示すために商品の価格を記した札。メーカーの出荷時点で既に付けている場合、流通の途中段階で付ける場合、小売店に商品が到着してから付ける場合など、そのタイミングはさまざまである。またショーウインドーなどで商品の近くに置いたものも含めて、値札と呼ぶことがある。
商品一つ一つに付ける例では、日用雑貨品のシール(ラベル・ステッカー)を直接貼る形式、衣料品などの糸・チェーン・タグピンなどで付ける形式が挙げられる。その他、補強の鳩目がある荷札のような種類もある。ほとんどの場合、紙・合成樹脂製である。
なお、バーコードの普及による会計作業の合理化も関与している。それに伴い、例えばスーパーマーケットでは値札の使用が少なくなっていった。青果物や店内で包装加工するその他の生鮮食品などを除き各商品置き場に1つの値札を設置し、まとめて掲示することで済ませる方式も増えている。そんな中、商品入替による処分価格販売のワゴンコーナーでは値札シールが今も用いられている。
![No.52 値札(ねふだ)]()
![No.52 値札(ねふだ) 裏]() No.52 値札(ねふだ) 裏
No.52 値札(ねふだ) 裏
↧
↧
November 16, 2014, 1:00 am
寝起きのアメリカ人に梅干しを食べてもらった ![梅干し]()
梅干しとは、ウメの果実を塩漬けした後に日干しにしたもので、漬物の一種である。日本ではおにぎりや弁当に使われる食品である。なお、塩漬けのみで日干しを行っていないものは梅漬けという。
すべての梅干しに共通した特徴として、酸味が非常に強いことが挙げられる。この酸味はレモンなどの柑橘類に多く含まれるクエン酸、調味梅干の場合はそれに加えて漬け原材料の酸味料に由来する。梅干しは健康食品としても知られる。
地方によって梅ではなく、近隣種である杏を使用する場合がある(岩手の八助梅など)。しそ梅を漬ける際一緒にした赤じそを乾燥させて粉末状にすると、副産物としてふりかけの一種である「ゆかり」ができる。
![No.53 うめぼし]()
![No.53 うめぼし 裏]() No.53 うめぼし
No.53 うめぼし
↧
November 16, 2014, 1:00 pm
板金 ヘコミの直し方!![軟鋼シートメタルの顕微鏡クローズアップ]()
板金・鈑金とは薄く平らに形成した金属である。その素材を常温で塑性加工することも板金・鈑金と呼ぶ。金属材料の基本的な形状の1つであって、切断加工や曲げ加工により様々な形状に加工することができる。たくさんの日用品がこの材料から作られている。一般的に、厚さが極端に薄いものを「箔(はく)」「ホイル(foil)」、6mm以上のものを「厚板」と呼ぶ。
板金は一般に材料をローラーに通して圧縮し、厚さ減らすことで6mm以下の板状に加工される。この工程は圧延として知られ16世紀頃に始められた。板金は平らな定尺だけでなくコイル状に巻いたものもある。
![No.54 板金(ばんきん)]()
![No.54 板金(ばんきん) 裏]() No.54 板金(ばんきん)
No.54 板金(ばんきん)
↧
November 17, 2014, 1:00 am
愛誓う「南京錠」はダメ! パリ・セーヌ川の名所(14/08/14) ![南京錠]()
南京錠はシリンダー錠の一種で、箱状の本体とU字型の金属の足「弦(ツル)」からなる。鍵で内部のシリンダーを動かすことで弦が持ち上がり、一方の足と本体の間に空間が生まれる。この空間にチェーンなどを組み入れてロックさせる。江戸時代初期には伝来しており、海外から伝わった「小さい」「珍しい」という意味で南京と名付けられている。例:南京豆、南京虫など
同じく江戸期に発展した「和錠」とは対を為す。最近の日本製の物では本体に真鍮、ツルにはステンレスまたは真鍮メッキした鋼鉄などが使われる。防犯性を高めるためツルを熱処理し硬度を高めた物もある。
![No.55 カギ]()
![No.55 カギ 裏]() No.55 カギ
No.55 カギ
↧
November 17, 2014, 1:00 pm
![トイレカギ]() トイレカギ
トイレカギ![トイレのカギ]()
トイレは多くの国で個室となっているが、中には仕切りのない国もある。また用を足したあとの始末には、トイレットペーパーを用いず水洗する習慣を持つ国もある。そのようなトイレは、インドやトルコのように、個室内に蛇口がある。水を用いる地域は気温の高い場所であることが多い。
世界的に見れば完全に他人の視線を遮断する日本式の公衆便所のほうが例外的でもある。日本人は排泄をする姿を他人に見られることを極度に嫌い、その逆に入浴を見られることは抵抗を感じない国民であると言われている。欧米では完全に密室にすることは、むしろ犯罪の温床となると考えられ忌避される。ドアも完全に視線を遮るものではなく、足の部分は外部から見える形式のものが多い。
![No.56 トイレのカギ]()
![No.56 トイレのカギ 裏]() No.56 トイレのカギ
No.56 トイレのカギ
↧
↧
November 18, 2014, 1:00 am
陣内智則 セミの1週間 ![終齢幼虫の羽化の様子]()
セミは、卵→幼虫→成虫という不完全変態をする虫である。日本の場合、成虫が出現するのは主に夏だが、ハルゼミのように春に出現するもの、チョウセンケナガニイニイのように秋に出現するものもいる。温暖化が進む近年では、東京などの都市部や九州などで10月に入ってもわずかながらセミが鳴いていることも珍しくなくなった。成虫期間は1-2週間ほどと言われていたが、これは成虫の飼育が困難ですぐ死んでしまうことからきた俗説で、野外では1か月ほどとも言われている。更に幼虫として地下生活する期間は3-17年(アブラゼミは6年)に達し、短命どころか昆虫類でも上位に入る寿命の長さをもつ。
鳴き声や鳴く時間帯は種類によって異なるため、種類を判別するうえで有効な手がかりとなる。たとえば日本産セミ類ではクマゼミは午前中、アブラゼミやツクツクボウシは午後、ヒグラシは朝夕、ニイニイゼミは早朝から夕暮れまで、などと鳴く時間が大別される。夏に多いとはいえ真昼の暑い時間帯に鳴くセミは少なく、比較的涼しい朝夕の方が多くの種類の鳴き声が聞かれる。
セミを捕えるのに失敗すると、逃げざまに「尿」のような排泄物をかけられることが多い。これは実際は飛翔の際に体を軽くするためという説や膀胱が弱いからという説もある。体内の余剰水分や消化吸収中の樹液を外に排泄しているだけで、外敵を狙っているわけではない。そのため飛翔時だけでなく樹液を吸っている最中にもよく排泄する。またセミの尿はほとんど水の便で、有害物質はほぼ含まれない。
![No.57 セミ]()
![No.57 セミ 裏]() No.57 セミ
No.57 セミ
↧
November 18, 2014, 1:00 pm
トイレ大小排水 レバー交換方法 ![水洗レバー]()
水洗トイレに「大・小」2つのレバーが付いているのは日本だけです。外国人からも非常にエコだと褒められる日本の水洗レバーです。
トイレの水流の「大」と「小」を使い分けるだけで、年間3000円以上の節約になります。水洗トイレのレバーは、「大」1回に付き約15ℓ、「小」で約10ℓの水を消費します。水道代に換算すると、1度のトイレの利用で平均2.5~3.75円です。よほど大きな大でなければ、小で流した方が水道代の節約になります。
水道代の節約として、「水洗トイレのタンクにペットボトルを沈める」という方法がよく知られています。一回の排水量を半分くらいに抑えて、節水しようというもの。これは間違った知識で、ペットボトルで節水は水づまりの可能性があるのでNG。最も一番の節約方法は、職場やコンビニ・スーパーのトイレで用を足した方が良いです。遺伝のため腹がいつも緩いオラは、出かける前に必ず大をしないと状態がよろしくないです。
![No.58 水洗レバー]()
![No.58 水洗レバー 裏]() No.58 水洗レバー
No.58 水洗レバー
↧
November 19, 2014, 1:00 am
THE MAKING (139)消しゴムができるまで![消しゴム]()
消しゴムとは、主に鉛筆などで書かれたものを消去するときに使う文房具。字消しとも呼ばれる。直方体のものが一般的だが、ボールペンのような形のノック式の消しゴムなども販売されている。色調は一般に白色のものが多いが、黒色など色付きのものもある。消しゴムが存在する前の時代は、パンを使っていた。
鉛筆で書いた線が消える原理は単純である。鉛筆で書いた部分には黒鉛(鉛筆の芯の成分)が付着。消しゴムでこれをこすると、ゴムが紙に付着した黒鉛を剥がし取りながら、消しゴム本体より消しかすとして削れ落ちる。更にその消しかすが紙から黒鉛を剥がし取りつつ包み込んで取り除く。紙からは完全に黒鉛が除去されて消しかすに移行し、消しゴムには新しい表面が露出する。以上のサイクルで消しゴムが減り、消しかすが出て字が消える。
![No.59 けしゴム]()
![No.59 けしゴム 裏]() No.59 けしゴム
No.59 けしゴム
↧

 どっきりシールが作られた1977(昭和52)年は、このような帽子掛けも多かったと思いますが、今では上の画像の例にもあるように大変モダンな帽子掛けがあります。普段の生活で帽子を必要としないので、帽子掛けについての思い入れは特にありません。
どっきりシールが作られた1977(昭和52)年は、このような帽子掛けも多かったと思いますが、今では上の画像の例にもあるように大変モダンな帽子掛けがあります。普段の生活で帽子を必要としないので、帽子掛けについての思い入れは特にありません。